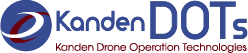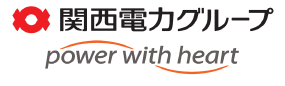学科試験とは
ドローン操縦における国家ライセンス「一等無人航空機操縦士」の取得要件として、
①一等学科試験の合格
②一等実地試験の合格(指定試験機関での試験or登録講習機関での審査)
③身体検査の合格
以上の3点が挙げられます。(二等の場合も同様です。)
今回は取得要件①の一等学科試験を受験して無事合格しましたので、試験に向けた勉強方法や、出題範囲となる問題を自作してみましたので、ご紹介していきます。
なお、過去に別の担当者が二等実地試験(指定試験機関での試験)を受験しておりますので、下記記事もぜひご覧ください。

試験概要
指定試験機関であるClassNKが管理している、無人航空機操縦士試験HP(https://ua-remote-pilot-exam.com/guide/written-examination/)から引用すると、試験概要は以下の通りです。
| 一等学科試験 | 二等学科試験 | |
| 問題数(三肢択一式) | 70問 | 50問 |
| 制限時間 | 75分 | 30分 |
| 合格ライン | 90%以上(63問以上) | 80%以上(40問以上) |
| 出題範囲 | 二等試験範囲+計算問題等 | 無人航空機の飛行の安全に関する教則 |
学科試験はCBT方式(PC上での試験, 全国の試験センターにて受験可能)で、三肢択一式です。
一等試験は全70問であり、二等試験と比較して20問多く出題されます。ただ、その分制限時間が長く、一問あたりに使える時間としては一等試験の方が多いです。
一方、一等試験の出題範囲については、二等の範囲に加えて計算問題等が追加されており、かなり時間を使いました。
※計算問題によっては、√(ルート)等を使った複雑な計算が求められる場合がありますが、PC上にて電卓が使用可能ですのでご心配なく。
一等・二等の学科試験をどちらも受験した身としては、圧倒的に一等の方が余裕は無かったです。
時間配分的には、回答時間60分(大体1問45秒, 計算問題は1問3分)、見直し15分が理想だと思います。
また合格ラインも一等だと90%以上となりますので、見直しの時間でいかに凡ミスを減らすことができるか、こちらも合格のカギだと思います。
勉強方法・勉強時間
個人的な勉強方法としては、下記の通りです。
①「無人航空機の飛行の安全に関する教則」の中で、出題されそうだと思う部分をマーカーでチェック。
②インターネットや市販の問題集から問題を解き、全問正解できるまで繰り返す。
③試験当日は、①のチェック部分をざっと確認。
なお勉強時間については、自分は所謂「追い込まれるまでやらないタイプ」なので、試験本番3日前から、1日5時間程度勉強したと思います。
ただ、自分は普段からドローン講習会にスタッフとして携わっており、ある程度の知識はあったので、一般で受講される方については、20~30時間は勉強時間を確保しておいた方が良いと思います。
(直近で二等試験を受講された方は、ある程度出題範囲が被っているので、もう少し勉強時間が短くてもよいと思います。)
筆者が自作した想定問題
前述した通り、一等試験では計算問題等も試験範囲となっております。
以下に、教則を基に筆者オリジナルの問題を自作しましたので、ぜひチャレンジしてみて下さい!
・無人航空機が揚力を失い落下を始めた場合、落下開始地点から地上に墜落するまでの水平距離が最も長くなるものとして、次のうち適切なものはどれか。ただし、空気抵抗は無視できるものとする。
①重量1kg, 飛行速度30m/s, 高度500m
②重量2kg, 飛行速度20m/s, 高度600m
③重量3kg, 飛行速度15m/s, 高度700m
(解説)
水平到達距離の公式 x=v√(2h/g)に選択肢の条件を当てはめて計算する。
(x:水平到達距離(m) v:飛行速度(m/s) h:高度(m) g:重力加速度(m/s2))
①の場合、
x=30×√(2×500/9.8)
≒303 m
②の場合、
x=20×√(2×600/9.8)
≒221 m
③の場合、
x=15×√(2×700/9.8)
≒179 m
よって、正解は①となります。
〇計算問題
教則p34「飛行性能の基本的な計算」記載の通り、飛行機および回転翼航空機の飛行に係る、以下の4つの計算が出題範囲となっております。
(1)飛行機の揚力・回転翼航空機の推力
(2)飛行機の旋回半径
(3)飛行機の滑空距離
(4)水平到達距離(水平投射の場合)
上記を計算するにあたり、それぞれ公式が存在するので、全ての公式を覚えておくことをオススメします。
また上記に加え、フレネルゾーンについての計算も出題範囲ですので、そちらもカバーしておくと良いと思います。
・カテゴリーⅢ飛行にてドローン飛行時の安全性確保措置を計画するにあたり、ロバスト性について、高レベルの安全性の措置が、低レベルの水準で保証された場合の安全確保措置のレベルはどれか。
①高
②中
③低
(解説)
ロバスト性のレベルは「安全性の水準」と「保証の水準」のうち、レベルが低い方に準じて評価され、今回の場合は「安全性の水準」が高、「保証の水準」が低 であるため、答えは③低 となります。
〇安全確保措置に係るリスク評価
教則p67「リスク評価のための基本的なコンセプト」記載の通り、一等試験では、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅢ飛行)」におけるリスク評価手法の活用も出題範囲となっています。
また上記のロバスト性の評価に加え、セマンティックモデル(想定飛行空間と想定外飛行空間)の考え方なども試験範囲ですので、十分理解しておきましょう。
以上、想定問題についての解説でした。なお紹介したテーマ以外で、以下も出題範囲となっておりますので、しっかりと勉強しておきましょう。
〇カテゴリーⅢ飛行における、飛行申請時の要件や許可されている飛行方法について
〇リチウムポリマーバッテリーの特徴やトラブル事例について
〇送信機から発信される信号に影響を及ぼす周辺環境・要因等について
今回は以上となります。今後も定期的に情報発信していきますので、ぜひご覧ください!